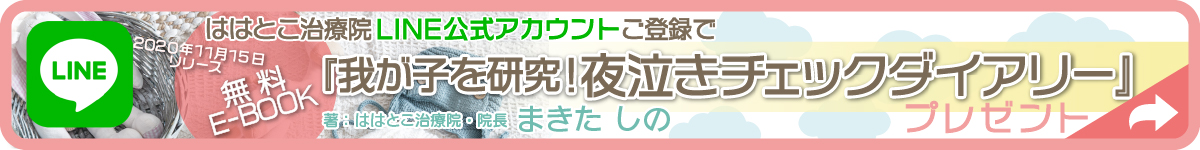発達障害は育つ!人は段階を踏んで成長する
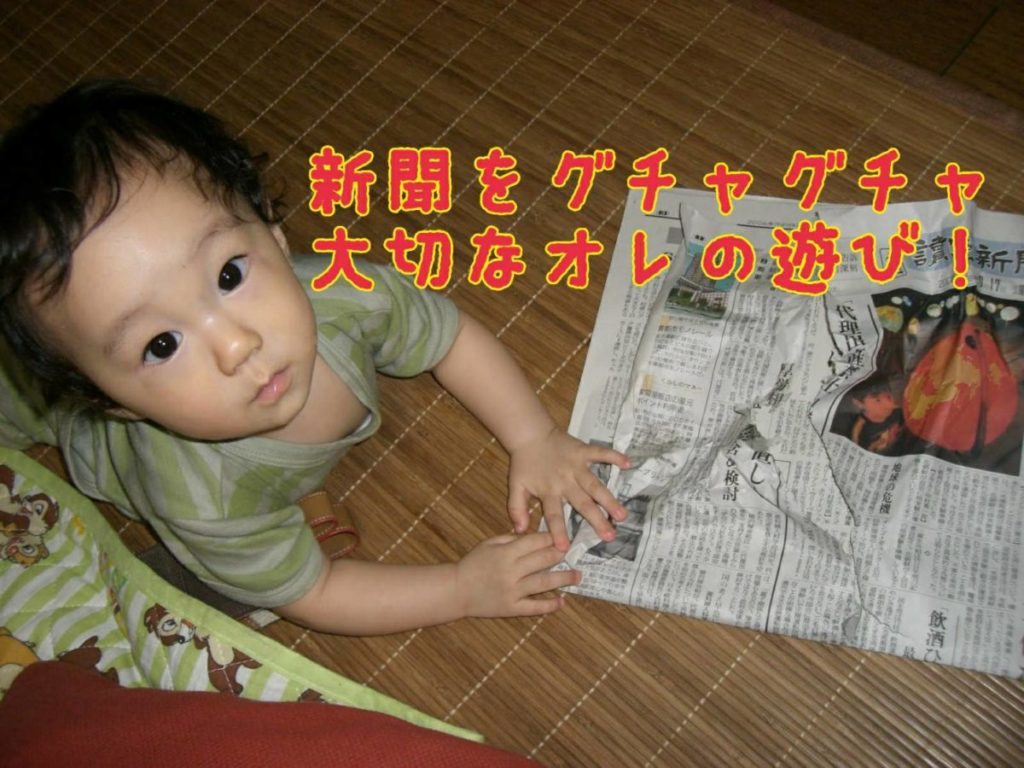
発達障害や発達の遅れ。
心配になるママたちは多いですね。
我が子も言葉が出るのが遅かったので、
その気持ちはよくわかります。
まわりの子と比べてできることが少ない
幼稚園や保育園での生活で困っている
健診で指摘を受けた
などなど…
発達障害、発達の遅れは取り戻せるのでしょうか。
発達の遅れや困りごとは「発達のヌケ」
赤ちゃんを見ているとみるみるうちに成長します。
表情も、体重も、泣き方、声の出し方。
月齢が低いほど、1週間前の様子とは違ってきますよね。
その成長、発達には段階があります。
- お腹の中で丸まった姿勢
- 産道を通って出産
- 初めての呼吸
- 首座り
- 寝がえり
- おすわり
- ハイハイ
- つかまり立ち
- 歩く

大きな流れで挙げてみましたが、
ハイハイ一つにしてもまず後ろに下がる動作やズリバイなど
細かい段階を経て次のステップに進んでいきます。
この段階のどこかが完成せずに成長すると
発達の遅れや上手くできないなどの困りごとが起きることになります。
これは「発達のヌケ」です。
また、赤ちゃんのうちは「原始反射」が残っています。
口の何か触れると吸おうとする「吸てつ反射」は
授乳をするのに必要な反射ですね。
また、驚いたり、刺激があると両手を上げる「モロー反射」や
指を差し出すとぎゅっとにぎる「把握反射」などがあげられます。

原始反射は大脳が発達していく、つまり成長ともになくなっていきます。
これらの反射が消失せずに残っていると
行動や感覚で困り感が出てきます。
個別の困りごと
- 不器用
- お友達とのトラブル
- 体の不調
- 言葉の遅れ
が「発達のヌケ」が原因であるなら、
そのヌケを戻すようにしてあげれば、
困りごとは大きく解決していくのではないかと思います。
☆栗本啓司先生の下記の著書、セミナーでのお話を参考にさせていただきました☆
「人間の根っこを育てる」栗本 啓司 (花風社)
発達、成長はその子それぞれの段階がある!
AちゃんもBちゃんもCくんも
見た目も違うし、性格も、体型も違います。
それと同じように発達や成長の仕方、速度もちがいます。
〇ケ月で何ができなければいけない
小学校に入ったら跳び箱は6段飛ばなければいけない
とか・・・
標準や大多数、世間で求められているものに合わせすぎると
その子の大切な発達の機会を奪ってしまうかもしれませんね。
その子を見て、その子自身の素敵な成長を見守りたいですね!
「これができないとダメ」なのではなく、
子どもの「これがやりたい!」をサポートできるといいなぁ、と。

「同じような遊びばっかり!」は
その子にとって必要な学びや運動、体づくりだったりするのですね。
鍼灸師、マッサージ師に何ができる?
「小児はりで発達障害がよくなりますか?」というような質問が時々あります。
私たち鍼灸師、マッサージ師は
発達障害かどうか?というような診断はあたりまえですができません。
小児はりはお子さんの自律神経に働きかけ、
リラックスしたり、体調不良を解消する手助けをします。
皮膚は感覚器であり、第三の脳。
触られるのが嫌だったお子さんが
小児はりやスキンタッチで感覚の過敏さが落ち着いたり、
ママとのスキンシップが心地よい!と
感じてくれるようになった例が多くあります。
お母さんのリラックスも
私たちにできることです。
お母さんがリラックスして子どもに接することが
お子さんにとって驚くほどのメリットがありますよ!